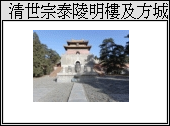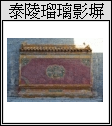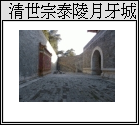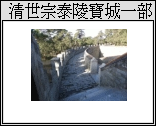關野貞 清陵調査より 東陵の世宗雍正帝泰陵 關野貞・竹島卓一他 撮影写真
關野貞・竹島卓一らの調査より、一部をご紹介します。
『関野貞日記』によりますと、關野貞は、大正7(1918)年7月31日と同8月1日に清朝陵墓の西陵を調査しています。「午前七時十分ノ列車ニテ橋本君ト共ニ出発〜〜先、雍正帝ノ泰陵ノ前面石物羅列ノ間ヲ過キ十七支里、道光帝ノ慕陵ニ至ル。此陵ハ帝ノ親ク築キシ寿陵ニシテ、規模倹薄ニ随ヒ後ノ標準トナリシ者、老栢叢裡殿門ヲ見、墳壟ヲ調査ス。殿堂ハ楠木ヲ以テ造リ、色彩ヲ施サザルハ他ニ見サル所ナリ。再泰陵ニ引返シ、石橋、石坊、碑閣、石物等調査、黄昏衛門ニ帰リ宿ス」(7月31日)、「〜先、泰陵ニ至リ、再碑亭、華表、石象、石獅、文武石ノ調査ヲナス。文石武石カ当時ノ服装ヲナセルハ面白シ、更ニ殿門墳壟ヲ歴覧ス。陵域ノ周囲一帯ニ二百年来ノ古松鬱蒼、支那ニ於テ他ニ見サル所トナス。次ニ其西方ニアル昌陵(嘉慶陵)ヲ見ル、前者ト同制度、唯規模小ナリ。午後、帰途ニ就キ光緒帝ノ陵ヲ過グ、陵ハ近年ノ経営ナレバ松樹僅カニ三、四尺ニ過キサルトモ地相ハ最佳ナリ、規模慕陵ニ似タリ、壁ハ赤キニ過キ、黄瓦ハ濃褐ニ過キ、多少不快ノ感ヲ起コサシム、而モ帝晩年ノ不幸ニ似ス兎ニ角堂々タル帝陵ナリ。午後四時発の列車ニテ、八時北京着」(8月1日)とあります。
この時撮影したと思われる写真が、工学系研究科建築学専攻に残されています。それを下記一番左の列にご紹介します。
また、わが東洋文化研究所にも、清朝陵墓の東陵・西陵の諸陵の写真が残されています。
關野貞『支那の建築と芸術』(岩波書店、1938年)の「薊県独楽寺」および竹島卓一『遼金時代の建築と其の仏像』(龍文書局、1944年)の自序によりますと、關野貞に率いられた一行は、昭和6年5月25日より北京郊外の東陵の調査を行っています。その時の調査は、關野貞・竹島卓一・建築家荒木清三・写真師岩田秀則によるものでした。關野貞や竹島卓一は、その調査の途次、薊県城内で中国最古の木造建築である独楽寺を発見するにいたったことを述べていますが、われわれは、それら(たとえば竹島自序)から、上記の人たちによる調査であったことを知ることができます。
わが所に所蔵されている東方文化学院(東京研究所)の記録によりますと、当時研究所の研究員であった竹島卓一から「建築写真」を大量に購入しています。想像ですが、これは、当時の東方文化学院の調査が關野貞研究員・竹島卓一助手のコンビでなされていたため、竹島が諸事をきりもりしていたためと思われます。そのため、この時の購入帳簿には、写真紙焼だけでなく、ガラス乾板原板も納入されています。現在なら、事後の支出になるのでしょう。
竹島からの写真紙焼とガラス乾板購入は昭和4(1929)年と6(1931)年になされ、そのうち6年購入分の中に、清東陵・西陵の写真があります。東洋文化研究所所蔵の東方文化学院の整理アルバムに、これらは整理されていますが、この整理アルバム写真は、その原板(ガラス乾板)とともに、昭和48(1973)年、『支那文化史跡』再販準備のおりに調査記録がつくられています(昭和48年12月調査。東文研蔵)。そのとき写真と原板が出版元たる宝蔵館に貸し出され、宝蔵館によって『東方文化学院東京研究所旧蔵写真印画帖明細表』が作られています。それには、鳥居龍蔵の写真(紙焼のみ)と關野・竹島のものとが区別されています。關野と竹島については区別されていない、ということですが、そういう扱いを受けていたということになります。
以上の経緯から、昭和6年と思われる清朝陵墓の調査写真は、關野貞ブランドの写真として扱うことにします。
昭和6年の調査写真は、關野貞大正7年の写真に示された基本に沿いつつ、撮影対象を拡大しています。下記においては、關野貞大正7年調査のものと比較して示します。關野・竹島「建築写真」の清陵関係写真は、世祖孝陵・聖祖景陵(以上東陵)・文宗定陵・西太后定東陵・世宗泰陵・泰東陵・仁宗昌陵・宣宗慕陵(以上河北易県の西陵)を調査対象にしています。これらから、大正7年調査対象である西陵の泰陵を示しておきます。
工学系研究科建築学専攻の關野整理写真と關野・竹島が整理したと思われる東文研の「建築写真」アルバムの写真では、被写体の配列順序が違っています。下記の配列順序は東文研アルバムによることにします。
ちなみに、關野・竹島「建築写真」の西太后の定東陵の写真には、1928年7月に孫殿英によって盗掘された後の調査であることを示すものがあります(西陵の西太后東定陵)。同じく盗掘後の撮影かとおもわれる写真が、もう一枚あります(東陵の康煕帝景陵)。この盗掘以後、写真や乾板が1931年に東方文化学院に収められる前の調査ということになります。
これもちなみに、ということですが、荒木清三は北平在住の建築家です。岩田秀則は別に紹介した北京の写真家です。岩田秀則を同行していますので、少なからざる写真は彼が手伝っていると思われます。ただし、東文研の購入(竹島卓一の名義)のあり方からしますと、別に購入した岩田写真は乾板がありません。これと違って乾板があるということですので、上記の岩田写真とは区別されるものだったと想像できます。当時の写真館は館主の名で複数の写真家が活動していたようなので、この時の活動は關野の下ということになり、結果として乾板までが納入されたと考えられます。
さらに述べておけば、『關野貞日記』によりますと、昭和3年12月4日に「晴 朝、天龍山仏頭ニ関シ服部博士ヲ訪フ。后四時鉢ノ木、彩華」とあった後、日記がとだえており、翌年元旦からの日録があります。その1月の日録の前に、「昨年十二月下旬、朝鮮高句麗時代ノ遺跡図版原稿上下二巻成リ、直チニ総督府ニ入札ノ手続ヲ依頼セントモ、年内に返事来ラス。」とあります。強いていえば、この時にも東陵・西陵調査にかかわった可能性は残ります。しかし、この前後、關野は多忙を極めていたようであり、明言されていないとはいえ、西陵の調査も上記の昭和6年のものと考えておきます。
「近況」の写真は、天津大学建築学院の青木信夫・徐蘇斌両教授との合同調査時のものです。お二人には、これまでお二人がなさってきた調査等の知見のみならず、現地とのやりとりなど準備の面でも大変お世話になりました。
以下、清西陵から、世宗雍正帝の泰陵調査をご紹介します。工学系研究科のものが大正7年關野貞調査、東洋文化研究所のものが昭和6年關野貞・竹島卓一調査です(整理の書き入れは竹島と思われます。池内節子氏にも確認していただきましたが若い時の字らしいとのことです)。他の諸帝の調査も基本的に同じ構図の写真が整理されています。關野貞の調査方針がわかる資料でもあります。
工学系研究科 東洋文化研究所 近況
建築学専攻の 關野貞竹島卓一等
關野貞整理写真 整理写真
○工学系建築学 ◇東文研乾板
専攻乾板あり あり
工学系建築写真を
あらためて焼付けた
ものといっしょに整
理されている

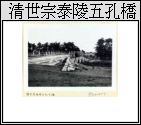


○ ◇ 工学系建築を利用



◇

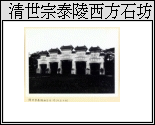
○ 工学系建築を利用


○ 工学系建築を利用


◇


◇
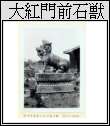
◇

◇
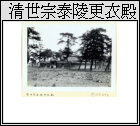
◇



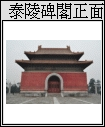
○ ◇ 工学系建築を利用

◇
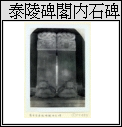
◇

◇


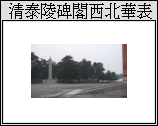
○ 工学系建築を利用

◇


◇

◇




○ ◇ 工学系建築を利用



○ 工学系建築を利用



○ 工学系建築を利用



○ 工学系建築を利用

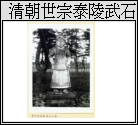
○

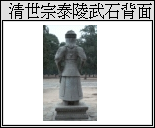
◇


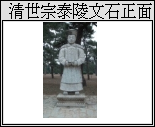
○ 工学系建築を利用


◇
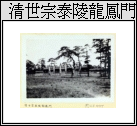
◇

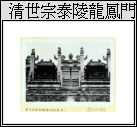

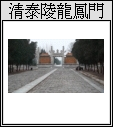
○ ◇ 工学系建築を利用

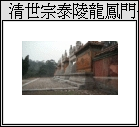
◇

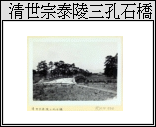
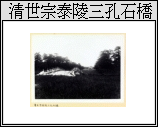
○ ◇ 工学系建築を利用


◇




○ ◇ 工学系建築を利用


◇

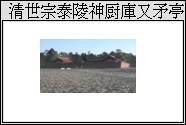
◇


◇
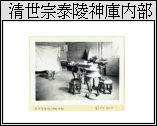
◇

◇

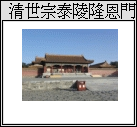
◇
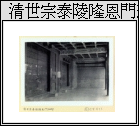
◇

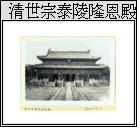

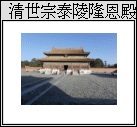
○ ◇ 工学系建築を利用

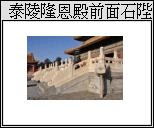
◇
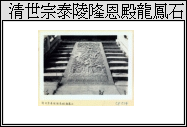

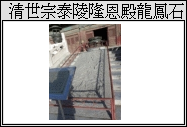
◇ ◇
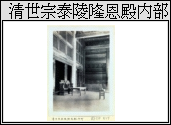
◇

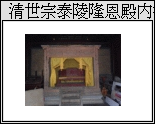
◇
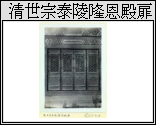
◇
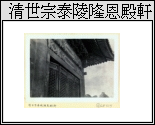
◇

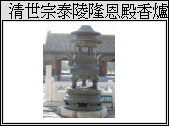
◇


◇

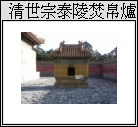
◇

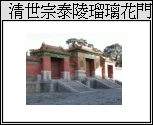
◇


◇

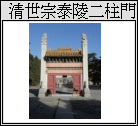
◇



○ 工学系建築を利用(明樓と言い換え)

 ◇
◇

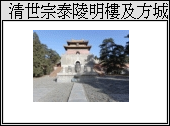
◇

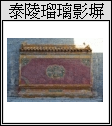
◇

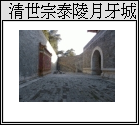
◇


◇

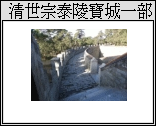
◇

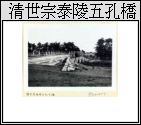






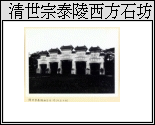






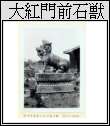

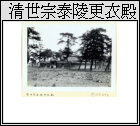



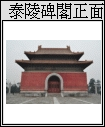

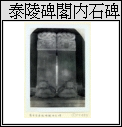



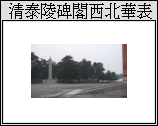


















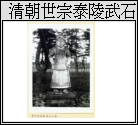

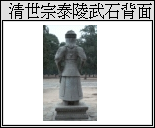


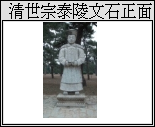


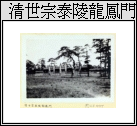

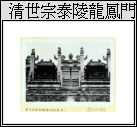

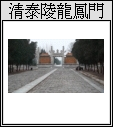

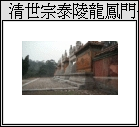

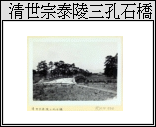
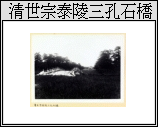









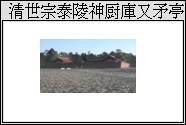


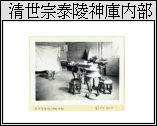


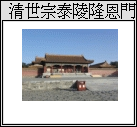
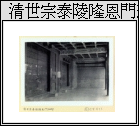

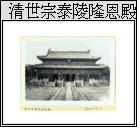

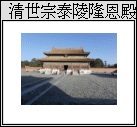

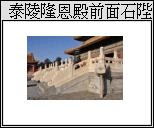
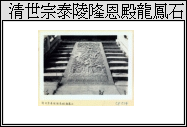

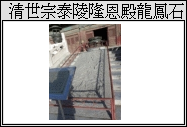
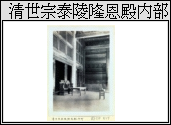

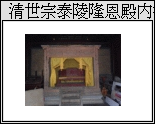
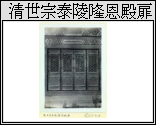
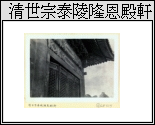

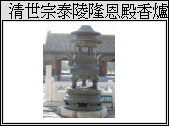



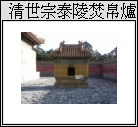

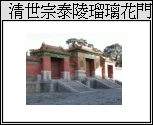



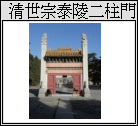




 ◇
◇