山本写真館古写真と關野貞整理写真 龍門石窟
下記には、山本写真館由来のガラス乾板写真と、關野貞の整理写真を対比して示すことにします。
東京大学人文社会系研究科考古学専攻には、「大和園・山本明写真場・東京青山」の手になる『龍門石窟』という写真帳が所蔵されています。その目次によると「大正五年九月・十年五月撮影」注とあります。そして、写真ごとに、写真の外に「大和園山本明 日本・東京」と注記されています。
この写真帳には、整理番号が付されており、これは目次の番号になっています。
わが東洋文化研究所には、山本写真館由来の古写真がありますが、そのうち、龍門関係のものは、この山本明の『龍門石窟』の原板であることがわかりました。ガラス乾板面に整理番号が貼られており、それが、『龍門石窟』と同じです。
なおかつ興味深いのは、このガラス乾板には縁取り(トリミンング)がなされており、その縁取り部分にも、被写体が写っていることです。山本明がこのトリミングをしたものと考えられます。東京都写真美術館の金子隆一氏とご相談しつつ確認したところでは、トリミングした周辺部で、膜が剥離する現象がみられ、この剥離もトリミングの理由の一つかもしれません。ということになると、写真を撮影した時期から、購入時までに劣化がおこったということかもしれません。
さらにより興味深いのは、このトリミンングがなされる前とそっくり同じ被写体のガラス乾板および紙焼きが、工学系研究科建築学専攻の關野貞整理写真として保存されていることです。しかも、その一部は、後に關野貞等の出版物『支那文化史跡』等に使用されていることです。
以上、今回進めた調査により、工学系研究科建築学専攻と東洋文化研究所に同じ被写体の同じ構図のガラス乾板がそれぞれ存在します。工学系研究科建築学専攻のものは、關野貞が利用し、東洋文化研究所蔵の旧山本写真館乾板は、山本明が利用しています。
上記の事実や、別にご紹介した日向康三郎氏の論文、および東洋文化研究所の記録、そして他に集めた情報から、われわれは、以下のようなことだろうと判断しています。
・關野貞の調査に山本明もしくは他の写真師が同行し、關野がさまざまに指示を出して写真撮影させた。
・山本明は、關野貞の委託(おそらく撮影に関する指示も)をうけて、別に機会を作って現地におもむき、写真撮影をした。
・山本明は、關野の指示に従って撮影を遂行し、その結果をガラス乾板と焼付けの形で關野貞に提出した。
・山本明は、撮影の際にガラス乾板つまり原板を2枚づつつくり、1セットを自らの下におき、1セットを關野貞に提出した。これは、一方のガラス乾板を原板、他方のガラス乾板を複製とした場合、原板から複製を作るには、原板→焼付け写真→複製という手順をふむ(原板から直接撮影すると、いわゆるポジのガラス乾板ができあがる)ことによる。こうした手間をはぶき、焼付け写真のゆがみなどを避けるには、そして、ガラス乾板が割れやすいという欠点をもつことから複製作成は必須だと最初から思っていたということであれば、2枚づつ撮影するのが合理的である。
・山本明のもとにあったガラス乾板は、後にご子息(山本讃七郎の孫)の山本茂によって東洋文化研究所に寄贈された。
・山本明は手元のガラス乾板をトリミンング処理して『龍門石窟』を複数作り、大学や研究所に頒布した。
・上記の東京都写真美術館の金子隆一氏によると、当時の写真館はいわばブランド経営をしていて、複数の写真家が同じブランンドの下で仕事をしていたので、まずは關野貞ブランドのものが支那文化史跡使用の工学系研究科建築学専攻整理写真となり、一方において実際の撮影者がトリミンング処理してみずからのブランドで写真集を作り販売した、ということのようである。
さて、山本讃七郎の下には、子の山本明以外にも、何人かの写真家がいたようですが、後に北京で独立し、やがて山本明帰国後に山本写真館をも引き継ぐ岩田秀則がいました。下記には、この岩田の写真も示しておきます。
わが所の記録(東方文化学院東京研究所の記録)によると、昭和9年9月11日付にて山本明より購入の「支那石窟焼付写真」631枚があります(昭和48年の調査時点で1枚欠)。これと同じものが、京都大学人文科学研究所にも所蔵されています。わが所の贓品は、戦前、東方文化学院東京研究所(後に名称がかわりました)が購入したもので、同じ東方文化学院として出発した京都研究所(後に名称がかわりました)とともに購入したようです。この「支那石窟焼付写真」には、一部を除いて大部分に「H. Iwata Peking」という注記が付されています。これは北京で山本写真館を引き継いだ岩田秀則のものです。
これらの写真の一部は、水野清一・長廣敏雄『龍門石窟の研究』(東方文化研究所、1941年)に利用されています。その序説に岩田写真に言及した部分があり、「〜ただ、大正十二年澤村専太郎教授は写真技師岩田秀則氏をともなひ、かなり詳細な調査をとげられたのであったが、惜しいかな、その成果は公表されなかったし、その記録もいまでは散逸してしまった。しかし、その岩田氏の写真は、また大正五年、大正十年に別に撮影された山本明氏の写真とともに北京で自由に分売せられたのであって、それがわが学界を裨益した点は少なくない(注:山本氏の写真は昭和十三年『龍門石窟』と題する焼付写真集として刊行された)。」とあります。
岩田秀則は、『北支在留邦人芳名録』(同発行所、1936年)によりますと、「明治十八年十二月六日生。明治三十九年一月北京に着。山本写真館に勤務すること四年、同四十三年独立して北京で営業。昭和五年十一月旧主山本写真館を継承」とあります。
したがって、大正12年の岩田の撮影は、岩田が山本写真館を引き継ぐ前、独立した後の仕事として引き受けたものであることがわかります。「H. Iwata Peking」という注記は、もちろんのこと今でいう版権主張の先駆けをなすものでありますが、直接的には、山本明の仕事と分けるという意味があるようです。
上記のように、東文研所蔵の山本明ガラス乾板写真のうち、龍門石窟は大正5(1916)年9月と大正10(1921)年5月に撮影されたもののようです。 その後、1920年代から30年代前半にかけて、石窟の破壊が進んだことが知られています(肥田路美「関野貞の中国彫刻史研究と石窟調査」藤井恵介他編『関野貞アジア調査』東京大学総合研究博物館、2005年)。破壊前の被写体を見ることができます。
關野の整理写真は、東京大学工学系研究科建築学専攻から提供を受けました。
山本の写真に●を付したものが、常盤大定・關野貞『支那文化史跡』(法蔵館、1939年)に再利用されているものです。トリミング画像が使われています(山本明トリミング後の写真)。
關野の日記(関野貞研究会編『関野貞日記』中央公論美術出版、2009年)によれば、關野たちは、大正7(1918)年6月7日から14日まで龍門を調査しています。これは龍門として二回目の調査で、一回目は明治39(1906)年です。日記によると、10月13日から18日までの調査でした。この時に關野に同行した写真師が誰であったかは、よくわかっていません。
關野整理写真の右に示しましたのは、岩田秀則の古写真です(岩田は戦後帰国し昭和37<1962>年4月死去)。
山本明 關野貞 磐田秀則 近況
東文研ガラス 整理写真 焼付け写真
乾板より 工学系研 東文研
龍門石窟 究科建築 ☆ 京大
表題(略言)と ○は工学系
番号は『龍門石 研究科建築
窟』目次による ガラス乾板
●支那文化 あり
史跡
1 関連画像
関連画像
2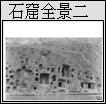
3
4
5
●6 関連画像
関連画像 
●7
●8 第一洞
第一洞
関連画像
「第二洞外壁」
●9乾板欠 関連画像 二・三・四洞外観 
10 関連画像 第二洞
関連画像 第二洞
11
12 関連画像 第三洞
関連画像 第三洞 
13

関連画像
14

15

●16
●17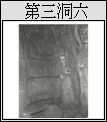
●18
 上記第三洞へ 現存せず
上記第三洞へ 現存せず
19 第四洞
第四洞
関連画像
20

21
22
 第五〜十洞外景
第五〜十洞外景
23

●24 ○
○ 第六洞
第六洞 

25 ○
○ 第十洞
第十洞 
26 ○
○
第十一洞
第十洞以南
第十二洞
27 関連画像 第十三洞
関連画像 第十三洞
28 頭部欠
頭部欠
●29
●30
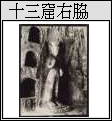
●31

関連画像 第十三洞〜
●32

33
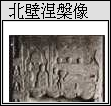
●34
 第十七洞北方
第十七洞北方
関連画像
関連画像
●35 第十八洞
第十八洞
●36
第十九洞〜
37 第十九洞
第十九洞 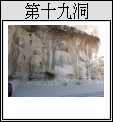
38

39
40
41
「第十九洞六」
42乾板欠
43

44
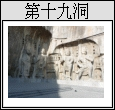
「第十九洞九」
45乾板欠
「第十九洞十」
46画像欠
●47
 第二十洞
第二十洞
関連画像
関連画像
●48
 第二十一洞
第二十一洞
「第二十一洞二」
●49乾板欠
「第二十一洞三」
●50乾板欠
●51 関連画像
関連画像
●52

関連画像
●53
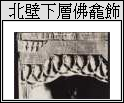
●54
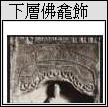
関連画像
55
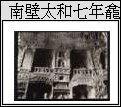
●56

関連画像
関連画像
57
58
石窟南端
●59 東山石窟
東山石窟
●60

 関連画像
関連画像 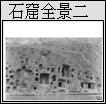



 関連画像
関連画像 

 第一洞
第一洞
 関連画像 第二洞
関連画像 第二洞
 関連画像 第三洞
関連画像 第三洞 







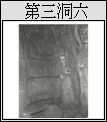

 上記第三洞へ 現存せず
上記第三洞へ 現存せず 第四洞
第四洞



 第五〜十洞外景
第五〜十洞外景

 ○
○ 第六洞
第六洞 

 ○
○ 第十洞
第十洞 
 ○
○
 関連画像 第十三洞
関連画像 第十三洞 頭部欠
頭部欠

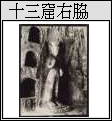





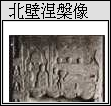

 第十七洞北方
第十七洞北方 第十八洞
第十八洞
 第十九洞
第十九洞 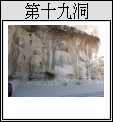








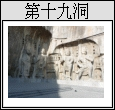

 第二十洞
第二十洞
 第二十一洞
第二十一洞  関連画像
関連画像


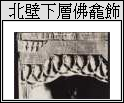

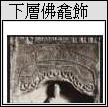

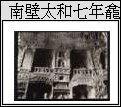




 東山石窟
東山石窟
